241127
この記事を閲覧するにはアカウントが必要です。
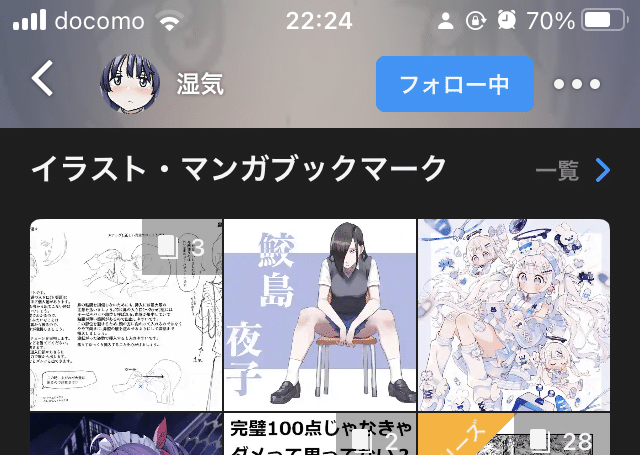
!!こっ……光栄ですッ!!ありがとうございます!!!
米津玄師にフォロバされるより嬉しいよね、こんなことは。権威付いた存在に承認されてうれし~みたいな一連のヤツは全然興味ないんだけど、この人に評価されるのは飢え満ちる荒野に一筋の供給を出来たと証明された気がして嬉しい。しかもこの人ほんと滅多に人の絵をブクマしないっぽいからな。少しは報いられたでしょうか、偉大なるあなたへ……。
ACG界隈って「変わらないものを愛でる」という性質がどうしてもある。キャラクターが数年経過して成長するみたいなのは賛否両論になるし、万人受けする作品というのはサザエさん時空みたいにキャラが一切変化せず、服も毎日同じものを着て、何年も何十年も「同じ世界」を繰り返すものが基本だ。
きょう気付いた。実はそこが「現実」と「空想」を分ける一番の境目なんじゃないだろうか。魔法だとかファンタジーだとかそんなちゃちなことではなく。「変わらない」という性質、その享受、その必然性とarbitraryさ、というのが、われわれが生きる現実世界における鉄の掟である「諸行無常」と真っ向から相反している。
よしんば変わるとしても、それは必然性に駆られたもので(進撃の4年後みたいな)、いわばこっちの都合で「変えている」にすぎず、時間という強制力によって無理やり「変えられた」わけではない。つまり、やはり空想世界は「諸行有常」「万物静止」が本質であり、成長だとか堕落だとかの属性ラベルと無関係の強制的かつ暴力的な流転性がない。また流転したとしても空想世界においては過去を過去のまま切り取って持ってくることができる。空想はどうあがいても空想である以上、「真なる姿」(=現実における”今”)がなく、過去も未来も同軸に存在しているからだ。(顧客の望まぬ)変化をし続けるRWBYに対するRWBY Chibiという静止世界、のように、「諸行無常」に叛逆することができる、というのが、リアルとアンリアルを分ける一番本質的な要素なのではないか。つまり空想と現実で最も大きく異なる要素。それに比べれば空飛ぶ箒も魔法少女もよっぽど「リアル」だ。
声優のラジオって人の性格が出るよね。如実に。特にどっとあいみたいなソロ喋りの奴だと株の乱高下が凄い。ていうか、基本下がるんですわ。声優なんてろくな人間がいないんだから。そんな中ひとりだけメチャクチャに株を上げた人間がいます。佐藤聡美……。
しゅがらじは善性。聴けば分かる。ああいう人間が好きなんです自分は。佐藤聡美みたいな、見かけ表面上すごいぽわぽわしていい人に見える人間が、蓋を開ければ本当にぽわぽわしていい人だったという稀有すぎる例。
むろん全16回のすべてがフェイクだったという可能性もなくはないが、複数人ならともかく一人喋りでそれは厳しい気がする。ボロが出るって絶対。
まあ、どうなんでしょうね。どっとあいを聴いて、良い人間だと思ってた人が実はメチャクチャ猫被ってただけで、悪い人間だと思っていた人が実はめちゃくちゃおっぴろげにしていただけで、両方の皮を剥いだら実は前者のがヤバい人でしたみたいなこともあるのかな。グルメレースの最後のボーナスの逆転みたいな。
戦争とASMRに広告をつける女が嫌いです。それについて自己弁護していた犬塚いちご及び類似する行為をしている人間が嫌いです。ASMRに広告をつける奴だけが落ちる地獄があるらしい。ぶち込まれる楽しみにしておいてください。
もうパターン化されたうつ病、うんざりなんだよ。大森靖子、Syrup16g、全部飽きた、面白くない。
バズについて、私は正体を述べることはできないが輪郭を述べることはできる。
- エラー発見の報酬である
- 感動と刺激の錯誤である
- グルーミングである
エラー発見の報酬という概念は実に画期的だったと思うのだけど(概念の発見というよりは概念を命名したという意味で)、あれ実際にはエラーである必要性はなくて、要するに発見の報酬なんですよね。
「発見」そのものがヒトにとって報酬であり、その希少度が高いほど、また「自分でなければ見つけられなかった」と思わせられる要因が多ければ多いほど効力は上がる。
おそろしく速い手刀 オレでなきゃ見逃しちゃうね
これも発見の報酬なわけで。いまやネットで冷笑ワードとなった「教養」だってそうです。与えられた文書の範囲では知り得ない、コンテクスト外の情報について、自分がたまたま既知であるとい状態を「学がある」と考え、それがそのまま「教養」という言葉の含意となったにすぎない。
「それはクリムトの絵みたいに」という歌詞が接吻を表現していると理解できるとか、フェイタルスピアの「人は負けるようには出来ていない」というセリフがヘミングフェイの『老人と海』の引用であるとか、そういった発見を得たときに「発見の報酬」が発動して気持ちよくなるってだけなんです。
インターネットの周り方ってマジでこれだけ。いかに大網を「あなただけの網」と思わせるかというマジックショーでしかない。性格占いとかもそう。当たり障りのない、誰にでも当たりそうなことを言っていれば「あたってる!」と勝手に思わせられる。言い回しややり方が巧いから気付きにくくなってるだけで。
自分が選別された、「選ばれた存在」だという実感が欲しいだけなんですみんな。バズの正体って生産側も消費側も此れしか無い。
谷川俊太郎はしきりに音楽への感動を訴えていた。音楽が起こせる感動は喜怒哀楽のどれでもないものなのだと。
私がそういう意味での感動をはじめて覚えたのはこの動画かもしれない。
https://sp.nicovideo.jp/watch/sm10782161
しかし私が音楽でおぼえる感動は結局コンテクストありきなところがある気がして、モーツァルトをはじめとしたクラシックを愛好する谷川俊太郎のそれとは異なる気がする。
https://twitter.com/denfaminicogame/status/1861681730304008695
実はずっと前から気になってはいたんです。今から始めるのってアリ?
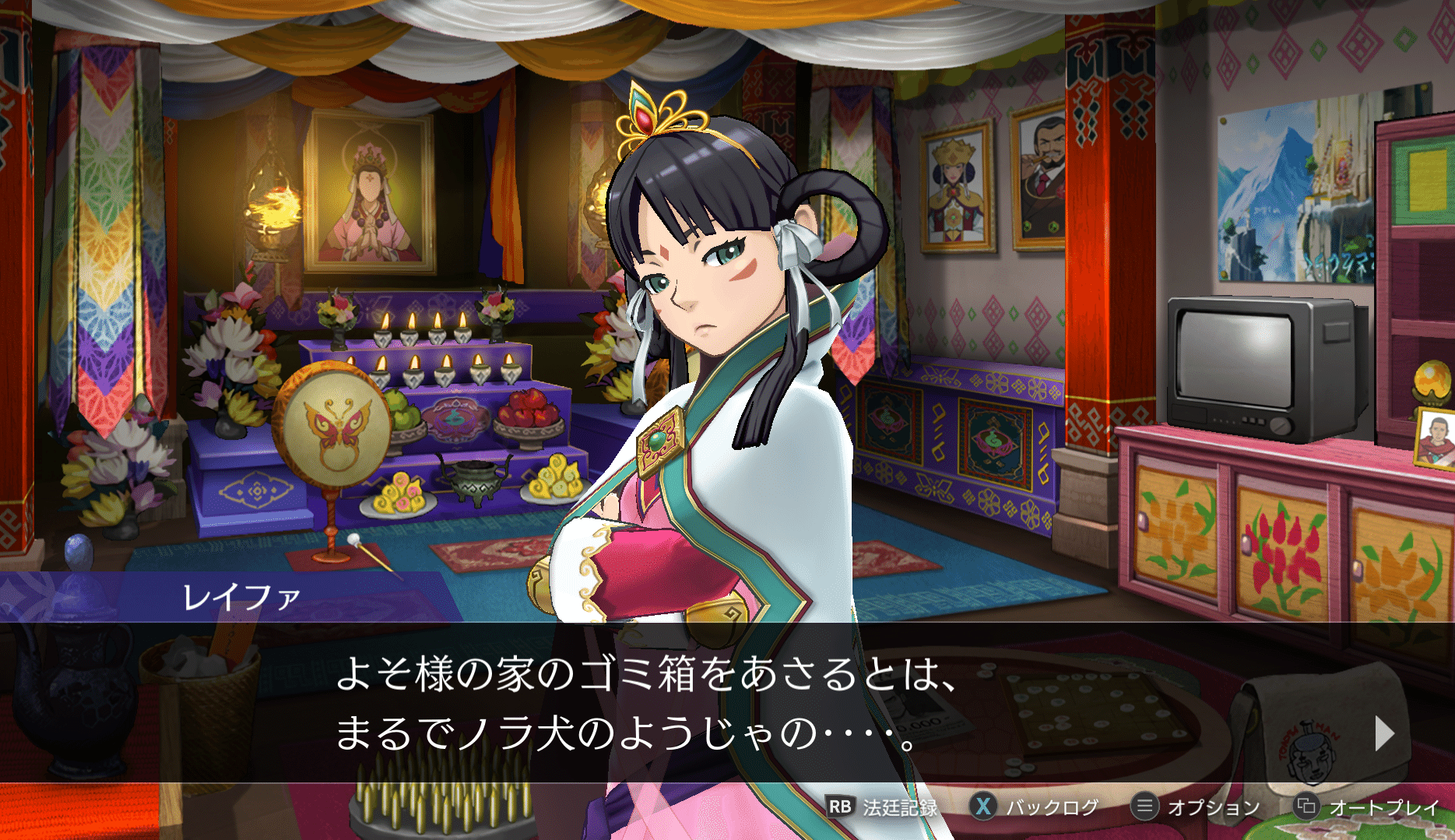
ありがとうございます!!!
逆転裁判6ってマジで不快なキャラクターしか出てこなくて、このレイファというキャラクターも1章時点では相当不快寄りだったんですが、3章から相方になってメチャかわいくなった。なんやろなあ。イヤなヤツなはずなのに、愛嬌があるというか……いや、多分別に嫌なやつでもないのよ。国民のことを気遣う優しさがあるし、少年に「弁護士を信じる」と言われてもいのいちに少年の心を守れなかった自分を責めだしたり、要するに「強く洗脳されているだけのふつうの少女」なんですよね。うまいわ~バランスが。このキャラに関してだけ言えば。ゲームオブスローンズみたいな好感度の変動の仕方してる。あれも好き嫌いが目まぐるしく変わるよね。サーセイの鬼火シーンで大喝采したでしょみんな。第一印象で相当嫌いになったキャラの好感度を回復させるのってかなり難しい気がしてるんだけど、レイファ様に至っては改心するとかそういうベタなageに頼らず素材そのままで回復させてるのが本当に凄い。嫌なヤツであることと好かれるキャラであることを両立させるためにはどうすればいいかという点で見習いたいな。
あとようやくこのNOTタクミシュウライターの性質が分かってきた。なんかおかしいと思ったら、あれです。前の記事で言った「他人の創作物を自分の世界としてスナッチする」という快楽に意識的であれ無意識的であれ酔っている。巧舟が造りあげたノウハウを破壊することへの快楽があるようですね。巧舟が嫌いというわけではなく(ハシゴネタのリファレンス等から見られるように)、彼への好意とか尊敬とは無関係に規定概念の破壊に快楽を覚えるタイプだと思う。+レベルファイブがよく陥る「露悪=刺激=おもしろさ」みたいなカスの三段論法錯誤を強く起こしている。今のところ見下げたライターと言わざるを得ないが、しかし彼が担当した5はかなり面白かったと思ってるし、どっちかというとライターというよりは制作進行を管理するディレクターが問題なのかもしれない。1章のナントカっていう犯人がゴミみたいな遅延行為連発するのは「開発側がプログラミングが難しかった部分をひけらかしたかっただけ」というのが真実だったらしいので、そこにストップをかけられなかったヤツが一番悪い。
記事の感想を伝えられます。
感想レターを書く
定型文を選択
スタンプを選択